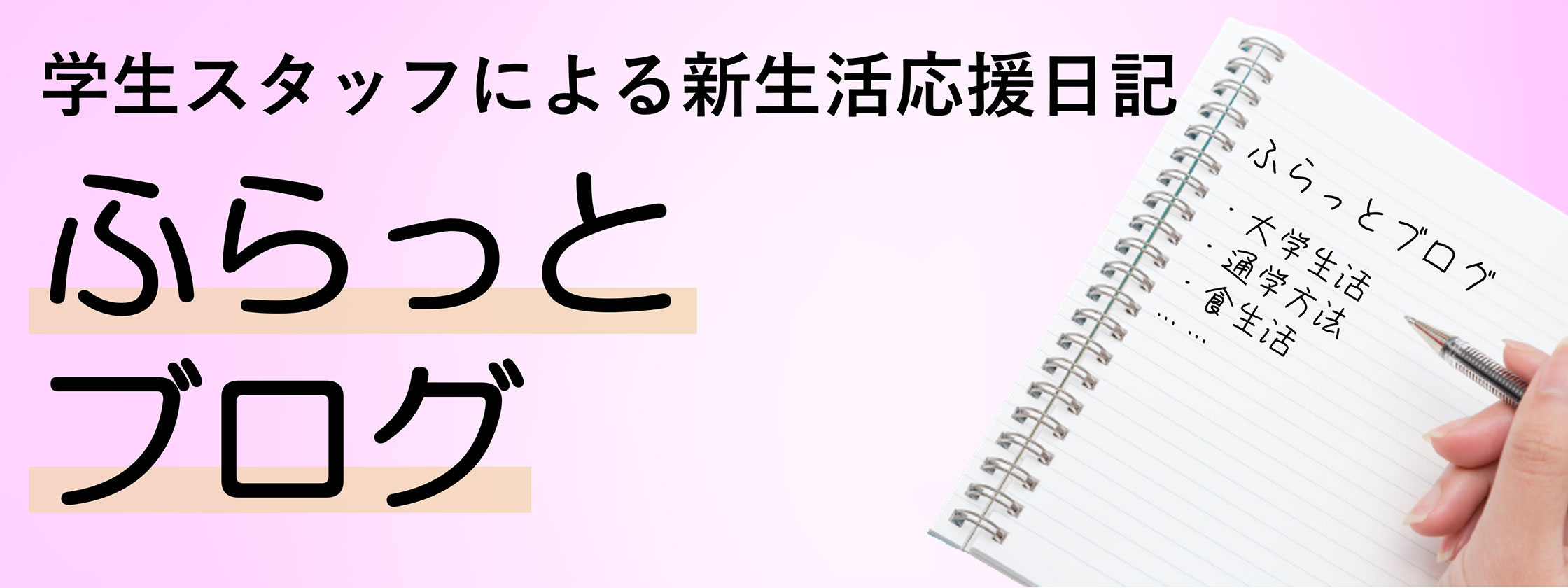皆さんこんにちは!理学部地球科学系地圏環境科学科3年の大野結生(おおのゆう)と申します。気づけばもう3年生ということで時の流れの早さを実感している今日この頃ですが、私の合格体験記が少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。私の学科は少しマイナーなのですが、簡単に言うと気候変動や自然災害、自然地形といったいわゆる「地球科学」という学問分野を扱っている学科です。地球を舞台にしている学問なので、高学年の専門教育になると野外実習があり、週1で山に入ります(アクティブな大学生活を送れます)。人数は30人と少なく、皆仲の良いアットホームな学科です。興味のある人は是非調べてみてください。
勉強面
私は11月頃に行われるAOⅡ期という受験区分で合格しました。この受験区分は、学部や学科で多少の違いはありますが、筆記試験と面接からなるものとなっています。私が受験した理学部地球科学系の試験は、一次試験が筆記試験と集団討論(筆記試験で出た問題についていくつか質問され、挙手して答える)、二次試験が面接と口頭試問、英語での短いスピーチという内容となっており、少しハードな試験でした。また、高校までは地球科学、いわゆる「地学」の内容は未履修の人が多いため、筆記試験や口頭試問の内容は専門的な地学の内容ではなくて、「科学的な思考力を問う」問題となっており、答えが明確でないために対策が難しいものでした(例えば、高校の物理や化学、数学の知識を用いて示された図表について解説する、など)。今考えると、地球科学そのものが物理学や化学、生物学といったさまざまな側面をあわせもつ複合的な学問であるため、その本質を問うていたのかもしれません…。
私がこの学科を志望したのは他でもなく、この「複合的な」学問ができるという点にあります。理科は好きだけれど「物理」・「化学」・「生物」はピンとこない(他の学科の皆さんごめんなさい)。そんな時、「地球科学」という、多岐にわたる内容を包括した、なおかつ身近なところで役立っているイメージの強い学問に惹かれました。私のように、「理科は好きだけど学科はどこにしよう」と悩んでいる人にはこの地球科学という分野をおすすめします。
私は出身が青森県で、同じ東北地方ということもあってか高校の先生方は東北大学への進学を推していました(あくまで私の感想です)。そんな雰囲気もあって高校入学と同時に私は東北大学を第一志望校にしていました。3年間を通じて学校の授業や定期テストに力を入れていたことから高い評定をとることができていた私は、先生方の後押しもあり3年の春ごろにAOⅡ期の受験を決めました。
得意科目:英語
理学部の私ですが実は得意教科はバリバリの文型でした(笑)。英語は授業が楽しかったのと、長文読解の時の、謎解きのような感覚が好きで当時の得意教科だった気がします。使っていた参考書は学校配布のものでした。長文読解は解くのにとても労力を使うと思いますが、文中のまとまりごとにカッコで括ったり、線を引いたりと自分なりに理解しやすいようにしるしを付けていくことで解きやすくなると思います。また、時間配分はたくさん練習して感覚として身につけておくと本番で焦らず解けると思います。
苦手科目:数学
数学は大学3年の今でも苦戦しています(大学の数学はもっと難解です)。当時は、少しでも苦手を克服しようと自分でノートを作ってひたすら解く、ということをしていました。ここで重要視していたのが、「無地のノートに解く」ということです。個人的な話かもしれないのですが、よくある方眼のついたノートに書くと綺麗に書こうとこだわりすぎてしまう気がして、少しでも本番の状態(定期テストや模試だとまっさらな用紙に解答しますよね)に近づけるために無地のノート(もしくはA4用紙)で演習を行っていました。また、授業は復習だけでなく予習も重視していました。はじめは「授業で当てられたときに皆の前で間違えたくない」という思いから教科書の問題を予習していたのですが、それが習慣化すると授業の理解度がぐっと上がることに気がつきました。数学に限らず苦手教科は、自分なりに対策を明確化・習慣化する(〇回正解するまで解く、難問を1日1個解く、など)ことで苦手を克服できるのではないでしょうか。
生活面
当時、生活面で意識していたことといえば「たくさん寝ること」でしょうか(テスト前・受験前なのにたくさん寝ていたので親から心配されたこともありました)。勉強で睡眠時間を削ってしまった次の日には計算ミスなどの凡ミスが増える気がします。毎日高いパフォーマンスを維持するためにも、しっかりと睡眠をとることが大切だと思います。寝すぎも注意ですが(笑)。
AOⅡ期を受験するにあたって
私が受験したAOⅡ期は、11月末にはもう合否が分かります。私の場合、共通テストや一般受験への勉強に本腰を入れる前に合格が決まったので、正直それほど受験勉強をしたという実感はありませんでした。そこで、一般受験の対策は他の皆さんにお願いすることとして、私はAOⅡ期の対策に特化してお話できればと思います。
①学校の授業が最優先
AOⅡ期の場合、受験資格は現役生のみ、また高校の評定平均が4.3以上(A段階)であることが求められます。これを踏まえると、学校の授業や定期テストにおける成績が重要であることが分かると思います。私は、参考書も学校配布のもののみ、塾にはまったく通っていませんでした。高校3年間で貫いていたのは「当たり前のことを確実にこなすこと」だけでした。この経験から言えるのは、学校の授業が何よりも大切だということです。さらに、学校の授業の復習として、家庭学習を重視していました。私は小学校からの家庭学習の習慣があったため、高校でも家庭学習ノートを作っていろいろな教科の復習をしていました。機械的な演習だけでなく、時には図表も自分で書いて理論ごとインプットすることで効果的な理解に繋げていました。高校時代は弓道部(週5で活動)に所属していたのですが、高校3年間を通して「時間が空いたら学校の図書館で勉強する」という習慣を付けていたため、部活との両立も苦ではありませんでした。
②AO受験の悩みどころ「志望理由書」
AOⅡ期・Ⅲ期を受験するには付きものの、志望理由書。正直、高校生のうちに「東北大学でこれがしたいんだ!」という大きな目標を見つけるのはとても難しいのではないかと思います。私もAOⅡ期の受験を決めた当時はまだ目標が漠然としていて、とても志望理由書を書けるような状況ではありませんでした。志望理由書で鍵となるのは「他の志望者との差別化」です。誰でも書けるような内容ではなくて、その人だけの着眼点や強い思いが書かれている必要があります。これを踏まえると、志望理由書を作成するうえで最も重要なことは「現状について調べる・知る」ことだと私は思います。この分野ではどこまで研究がなされていて何が分かっていないのか知り、そのうえで自分は何をしたいのか考える、このようなプロセスを繰り返すことで東北大学での自分の将来像が具体性を帯びてくると思います。そこで東北大学のホームページを見てみると各研究室でどのような研究をどのような手法で研究しているのか明確に知ることができます。さらに、私は高校の先生の勧めで科学雑誌(Newtonなど)やブルーバックス(講談社)を読み、少しずつ自分の目標を明確化することができました。「調べる・知る」作業を通して新たに得られるものはたくさんあるので、それによって志望理由書への苦手意識も少しは薄れるのではないかと思います。私のように高3になってから焦らないように、皆さんには高校1・2年のうちからたくさん大学や学問分野について詳しく調べることを強くおすすめします。
③AO入試で測られる能力って?
冒頭でお話ししましたが、私の学科のAOⅡ期の試験には筆記試験の他にも面接や集団討論、英語での短いスピーチといったものが科されていました。このことから、AO入試で測られるのは学力だけではなく、コミュニケーション能力や主体性といった部分も重要であることが分かります。このような力を養ううえで、私の場合、高校の探究学習が大きな自信に繋がりました。私の高校はSSH(スーパー・サイエンス・ハイスクール)に指定されており、様々な研修やプログラムが充実している環境にありました。私は高校2年生の冬にSSHの特別研修に参加し、ベトナムの高校とオンラインで探求学習での研究の発表を行いました。この研修に参加したことで普段の授業では培われないような能力(発信力や課題解決力など)が養われたと感じており、それがAO入試に直結して役立ったと思っています。AO入試の受験を考えている人は、探求学習の授業に力を入れて取り組んだり、こういったイベントに参加してPRポイントを増やしたりしてみても良いかもしれません。
受験前日・当日の過ごし方
受験前日は、今まで解いた過去問を眺めたり、面接での受け答えについて軽くシミュレーションしたりする程度で、ゆっくりと過ごしていました(お気に入りのテレビドラマも見てしまったくらいです)。早めに就寝し、明日の試験に備えました。
一次試験(筆記試験・集団討論)の当日は、緊張からか朝ごはんは全く食べられませんでした。両親に会場まで見送られ、緊張しながら席に着いたのを今でも覚えています。肝心の試験はというと、今までの過去問の対策もあってか冷静に思考し問題を解くことができました。集団討論は他の受験者がたくさん発表している中で焦りましたが、「意見を言わなければ落ちる」という気概で何とか乗り切りました。余談ですが、私以外の受験者は皆標準語を話していて、地域間ギャップを感じたのがショックでした(私は津軽弁丸出しで行きました)。
二次試験(面接・口頭試問等)の当日も朝は食事がのどを通りませんでした。大学の先生と直接話すということでとても緊張し、呼ばれるまでの時間が永遠に感じられました。いざ面接会場に呼ばれると、先生方4人に対して私ひとり。緊張で押しつぶされそうでしたが、フレンドリーな先生方と会話するうちに徐々に慣れていき、全体的には淀みなく話すことができたと思います。
最後に
ここまで長々と私の合格体験についてお話ししてきましたが、読んでくださった皆さんにとって何か得るものがあれば嬉しい限りです。3年前に勝ち取った「合格」で、私の周りのたくさんの人が私以上に喜んでくれました。その姿を見たとき、多くの人に応援されて、支えられてきたことを痛感しました。そしてあれから早2年半、現在はこの東北大学で勉学に励むせわしない日々を送っています。これを読んでいる皆さんは、合格できるか不安な日々を送っているかもしれませんが、最後まであきらめずに自分を信じて、そして周りの支えてくれる人たちへの感謝を忘れずに、突き進んでいってください!皆さんが合格されることを心より願っております!