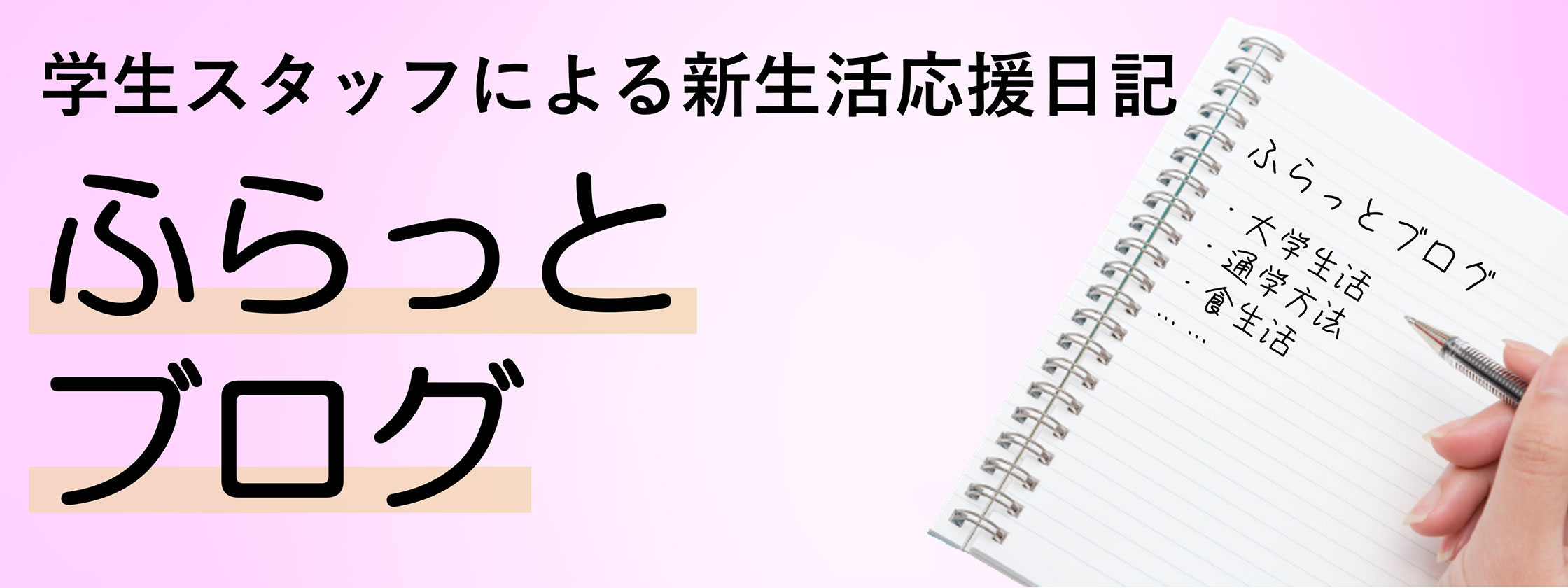こんにちは!法学部2年の宮城島颯太です。私は一般入試(前期日程)で東北大学に合格しました。志望校として東北大学を意識し始めたのは比較的遅い時期でしたが、講義を受けるうちに、「この大学に入ってよかった」と心から感じるようになりました。この合格体験記が、皆さんの受験勉強の参考になれば幸いです。
勉強面
受験区分および志望決定までの経緯
私は共通テストの自己採点を行った後、東北大学を受験することを決めました。もともとは他の国公立大学を志望していたのですが、社会が不得意で、その志望校の合格点に届かなかったため、現時点の学力で合格の可能性があり、かつ最も難易度の高い大学として東北大学を選びました。法学部を目指した原点は、小学生の頃に見た弁護士ドラマです。冤罪を晴らすために難事件に立ち向かう主人公の姿に感動し、「自分もこんなふうに人を助けられる弁護士になりたい」と強く思ったことを今でも覚えています。
勉強時間と学習環境
高校3年生の夏休み前まで部活動を続けていたこと、そしてゲームがなかなかやめられなかったこともあり、それまでは宿題や定期試験対策、数学の問題集に少し取り組む程度でした。私は、環境が整っていないとすぐにゲームに手を伸ばしてしまう性格だったため、夏休みからは塾に通うことで、ほぼ毎日10時間ほど勉強するようになりました。
塾では基礎から共通テスト・二次試験対策まで幅広く取り組みました。夏休み明けからも放課後は高校に残って夜まで勉強するか、塾へ行き22時頃まで机に向かう日々が続きました。今思い返すと、学校や塾への送り迎えを毎日のようにしてくれた両親には感謝の気持ちでいっぱいです。
共通テストの1か月前からは、共通テストの過去問を何度も解くことによって出題形式への慣れを重視しました。共通テスト後は私立大学の対策にはあまり手をかけず、東北大学の二次試験対策一本に絞って学習しました。東北大学の法学部で出題されるのは国数英の3科目だったため、どの科目も旧帝大を中心とした難関大の過去問を、高校の先生に1対1で解説していただきながら勉強していました。大学によって出題形式は異なるため(当時の私は気づけませんでしたが)、併願される方はその大学の過去問には一度目を通しておくことをおすすめします。実際、私は東北大学の受験前夜に初めて英作文の存在を知り、心臓が止まりました。
得意科目:数学
私は幼い頃から算数が好きでした。複数のアプローチから1つの答えにたどり着ける自由さや、暗記よりも思考力や計算力が試される点に、数学の大きな魅力を感じていました。そのため、中学3年生のときには学校指定の黄チャート(ⅠA・ⅡB)を1周解き切り、高校入学後は赤チャートをやり切りました。もとから数学は得意でしたが、そのおかげで更に基礎を固め、更に応用問題にもある程度対応できるようになっていたと思います。問題集には相性があるので、難しいですが自分に合ったものを見つけられると勉強が一気に進めやすくなると思います。
私は、難問に出会うと1問に何時間も考え込むようなタイプで、解けたときの達成感や優越感をモチベーションにしていました。ただ、数学が苦手な方には「わからなければ解法を見て理解し、再度解いてみる」「数日後に再挑戦する」という学習法がおすすめです。特に文系数学は凝った問題が多く、思いもつかないようなアプローチをしなければ解くことができないという問題も多いですので、何のヒントも経験もないような状態で解こうとしても時間を浪費してしまうだけになってしまいがちです。
苦手科目:社会
私は日本史選択でしたが、どうしても社会は暗記の側面が強く、暗記が苦手な私には無理でした。「流れやつながりを意識して覚えるべき」とよく言われましたが、結局は人名や単語の暗記が必要で、私には向いていませんでした。むしろ、二次試験で社会科目が不要な東北大学は、自分に合った大学だったと感じています。
私の日本史対策は主に2つです。1つは共通テストの過去問を繰り返し解き、問題そのものを覚えてしまうこと。まったく同じ問題は出ませんが、選択肢まで覚えるくらいまで何度も解くと類似問題で正答を選びやすくなります。もう1つは、時系列でのノートまとめです。1年弱かけてとってもきれいなノートを作っていましたが、明治時代半ばまでしかまとめることはできませんでした。それでも、自分で作ったノートを元に勉強することで、情報の整理がしやすくなりましたし成績も伸びました。きれいなノートを作ることに重点をおきすぎて肝心の知識を身に着けられなくなる、と心配する方もいるかもしれませんが、日本史の勉強をしたくなかった私でもノートづくりは楽しく、教科書や資料集に目を通すきっかけになったので、結果として学力の向上に寄与していたと思います。
もちろん倫理・政治経済も苦手だったため、ノートづくりはしなかったものの、日本史と同じように共通テストの過去問を大量に解いて、本番で知っている問題に当たることを祈っていました。
生活について
勉強以外の時間を大切にする
私はずっとゲームが好きで、スマホやパソコンでよく遊んでいました。特に高校生になってからはPCゲームに熱中していたのですが、3年生に進級するタイミングでパソコンが壊れてしまいました。当時はショックでしたが、それにより必然的にゲームの時間が減り、結果的に勉強に集中できるようになったのは大きかったです。それまで私は、帰宅するとすぐにパソコンを起動し、何時間もゲームや動画に没頭する生活を送っていたため、ゲームをする手段がなくなったことで生まれた空白の時間を、勉強に充てることができました。とはいえ、趣味や息抜きをすべて断つのは精神的によくありません。実際、受験期でも私は毎日ゲームをしていて、親によく叱られていましたが、全くゲームをしなかったらストレスで勉強にも集中できなかったと強く思います。ちなみに塾で毎日勉強していた時期も、勉強に疲れたら外に出てちょっと離れた公園を散歩をしたり、行ったことのない道を探検したりして息抜きをしていました。
勉強の習慣を作る
私は、数学以外の勉強があまり好きではなく、自分から積極的に取り組むことはほとんどありませんでした。高校3年生になって塾に通い始めたのも、「勉強せざるを得ない環境に身を置くこと」が目的でした。勉強しなければならないと頭では分かっていても、どうしても他のことに気を取られてしまうという人も多いと思います。そういった場合は、自分にとって勉強せざるを得ない環境を意図的に作り、毎日決まった時間や場所で勉強することを習慣づけることも1つの手です。そうすることで、次第に勉強すること自体に慣れていくはずです。それが、勉強を始めるための第一歩になります。
受験前日・当日の過ごし方
併願した私立大学の受験でも同様でしたが、私は前日・当日ともに、問題演習は一切しませんでした。「今解いて分からなかったら不安になる」という気持ちがあったのも一因ですが、それ以上に、「ここまで頑張ってきた」という自信と、受験地である東京や仙台を訪れること自体が楽しく、旅行気分だったというのもあります。そのおかげもあって受験前後はほとんど緊張していませんでした。前日に現地入りし、母と受験会場を下見しながら街の景色を楽しみました。特に東北大学の受験前日は雪が積もっていて、雪にほとんど縁のない静岡出身の私にとっては、雪玉を作ったり、雪だるまを見たりするだけで楽しい思い出となりました。
また、睡眠時間は当日のパフォーマンスに直結します。早めに就寝して試験に備えることも、非常に重要だと感じました。
併願校
先述のとおり、私は数学が得意で社会が苦手だったため、併願校も社会を課さず、代わりに数学で受験できる大学に絞りました。高校の先生からは「数学受験はリスクが大きい」と止められましたが、私の場合は社会が「上振れ」したときよりも、数学が「下振れ」したときの方が成績が安定しており、何より数学に強い自信がありました。自分の得意科目を信じて進んだことで、良い結果につながったと思います。近年は、得意科目を活かせる受験方式が増えています。ぜひ情報を集めて、自分が戦いやすいフィールドを見つけてみてください。以下に、私が受験した併願校を挙げておきます。全て法学部法学科、一般においては社会を課さず、数学を課す方式を選択しました(明治大学の一般は不合格でしたが、他は合格できました)。
・中央大学(共通テスト利用・一般)
・明治大学(共通テスト利用・一般)
・法政大学(共通テスト利用)
最後に
受験のゴールは何かと聞かれたら、私は迷わず「志望校に合格すること」だと思います。もちろん、合格がすべてではないという考え方もありますが、受験生にとって一番明確で大きな目標は、やはり合格ではないでしょうか。だからこそ、そこに向かって全力を尽くすことには、確かな意味があります。そして、そのゴールの先には新たなスタートが待っています。
受験勉強はつらいと感じることもあるかもしれませんが、積み重ねてきた努力は必ず力になります。合格というゴールに向かって、今できることをひとつひとつ着実にこなしていってください。この体験記が、少しでも皆さんの助けや励ましになれば嬉しいです。心から応援しています。次は東北大学でお待ちしています。