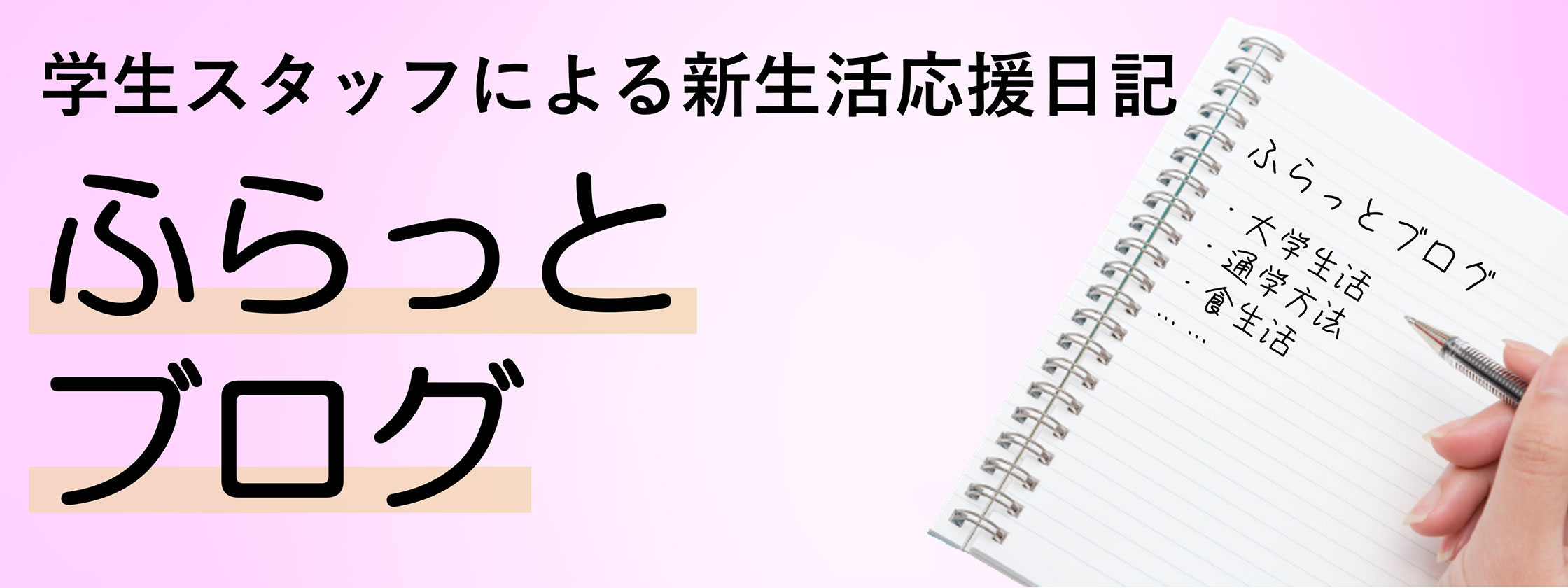こんにちは!農学部植物生命科学コース2年の江良風花です。今回は私の受験の話について書かせていただきました。参考程度に気楽に読んでいただけると幸いです。
勉強面
私が東北大学を志望したのは、自分が興味のある分野の研究をされている先生がいらっしゃったからです。大学では研究に力を入れて取り組みたいと考えていたため、整った設備やハイレベルな環境にも魅力を感じました。
また私はAOⅡ期という受験区分で受験しました。試験内容は学部によって異なりますが、私が受験した農学部では、一次試験が筆記(数学、理科2科目、英語)、二次試験が小論文と面接でした。高校の先輩にAOⅡ期で実際に合格された方がいて、先生方からも話を聞いていたので、1・2年生の頃から少し意識はしていましたが、最終的にAOⅡ期での受験を決めたのは高校3年生の5月頃だったと思います。
得意科目:生物
生物はもともと好きな科目で、ミクロな細胞の働きからマクロな生態系や環境まで幅広く学べる点や、身の回りのさまざまな現象を自分の言葉で説明できるようになることに魅力を感じていました。勉強法として特別なことをしていたわけではありませんが、「なぜそうなるのか」を自分で説明できるよう意識しながら学ぶようにしていました。また、持っている知識を考察問題などでどのように活用するかが大切だと感じていたため、資料集の読み込みに加えて、演習にも力を入れて取り組んでいました。
苦手科目:化学
化学の中でも、特に有機化学には苦手意識がありました。ですが、分からない箇所は毎日のように先生に質問しに行き、毎日少なくとも1題は有機化学の大問を解くことを習慣にすることで、徐々に問題が解けるようになっていきました。勉強を進める中では、感覚やなんとなくで解答することを避け、論理的で再現性のある解答ができるようになることを意識して取り組んでいました。ただ、基礎にこだわるあまり演習に取りかかるのが遅れてしまったことは、自分の中での反省点です。
生活について
1. 1日のルーティンを作ること
起床時間や就寝時間を固定することはもちろんですが、一日の流れをある程度ルーティン化することで、勉強への抵抗感がなくなり、自然と机に向かう習慣が身についたと思います。その結果、勉強を始めるまでの時間が短くなり、効率や時間の使い方も向上したと感じています。
2. 自分なりの気分転換方法をつくる
家の周りに勉強に使える施設がなかったため、基本的に自宅か学校で勉強していましたが、その中でも飽きずに取り組めるよう、いくつか工夫をしていました。たとえば、勉強内容を時間帯ごとに分けてメリハリをつけていました。朝起きてから朝食までは英語の長文、車の中では英単語、放課後の学校の自習室では数学、帰宅後から夕食まではリスニング、夕食後から就寝までは理科、というように、場所は限られていても時間で区切ることで、気分を切り替えながら勉強していました。これはあくまで私の例ですが、ちょっとした気分転換で、集中力を保ちながら勉強することは大切だと思います。
3. 学校の授業をしっかり受けること
一度挑戦してみたこともあったのですが、不器用な私には内職は向いていませんでした(笑)。ただAOⅡ期での受験には一定の評定平均値が必要ですし、文系科目の授業を集中して聞くことで放課後の時間を理系科目の自習に費やすことができ、授業をしっかり受けて良かったと思うことが多かったです。
受験前日・当日の過ごし方
受験前日:受験前日は何かしていないと落ち着かず、過去問などを見直して過ごしました。特に1次試験の時は最初の受験と言うこともあり、前日から既に緊張していた気がします。一通り勉強した後は、いつもと同じくらいの時間に布団に入って次の日の試験に備えました。
受験当日:当日は遅れないように、早めにホテルを出発しました。AOⅡ期は一般入試に比べて受験者数が少ないとはいえ、地下鉄は少し混雑していたと思います。会場に到着すると、周囲の人たちがとても賢そうに見えて不安になりましたが、過去問などを見直しながら試験開始を待ちました。試験が始まってからは、解ける問題が増えていくにつれて気持ちが落ち着き、最終的には冷静に試験に臨むことができました。
併願校
なし
最後に
ここまで私の拙い文章を読んでいただきありがとうございました。受験をするにあたっては大変なこともたくさんあるとは思いますが、周りの人達への感謝を忘れずに、最後まで頑張って下さい!応援しています!